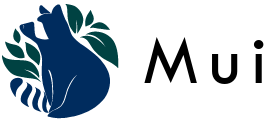【動物利用事業】トカラヤギの除草実証実験について聞き取りを行いました【兵庫県】
2024年4月から10月にかけて、兵庫県養父市が、トカラヤギを使った除草の実証実験を行いました。
養父市記者発表資料「厄介な雑草はヤギにおまかせ!」養父市でユニークな取り組み(サンテレビ)
目的は、施設管理の省力化と脱炭素化。業者から「アンディ(オス)」「リリちゃん(メス)」という2頭のヤギ(当時2歳)をレンタルし、市の施設にて実施したそうです。
そして先日、実験結果についての報道がありました。
ヤギの除草実証試験 成果は期待外れ 好き嫌い、急死… 兵庫県養父市(産経新聞)
記事によると、
・レンタル元は奈良にある業者
・職員らが3日に1回、飲み水の世話や除草の状況を確認した
・8月にアンディが原因不明で急死、業者から新たなヤギをレンタルして除草を続けた
・9月にリリちゃんが出産(1頭)
・レンタル料に見合う除草効果は見られなかった
とのことです。
当記事で実験の存在を知った私たちは、詳細確認のために養父市役所を訪問しました。
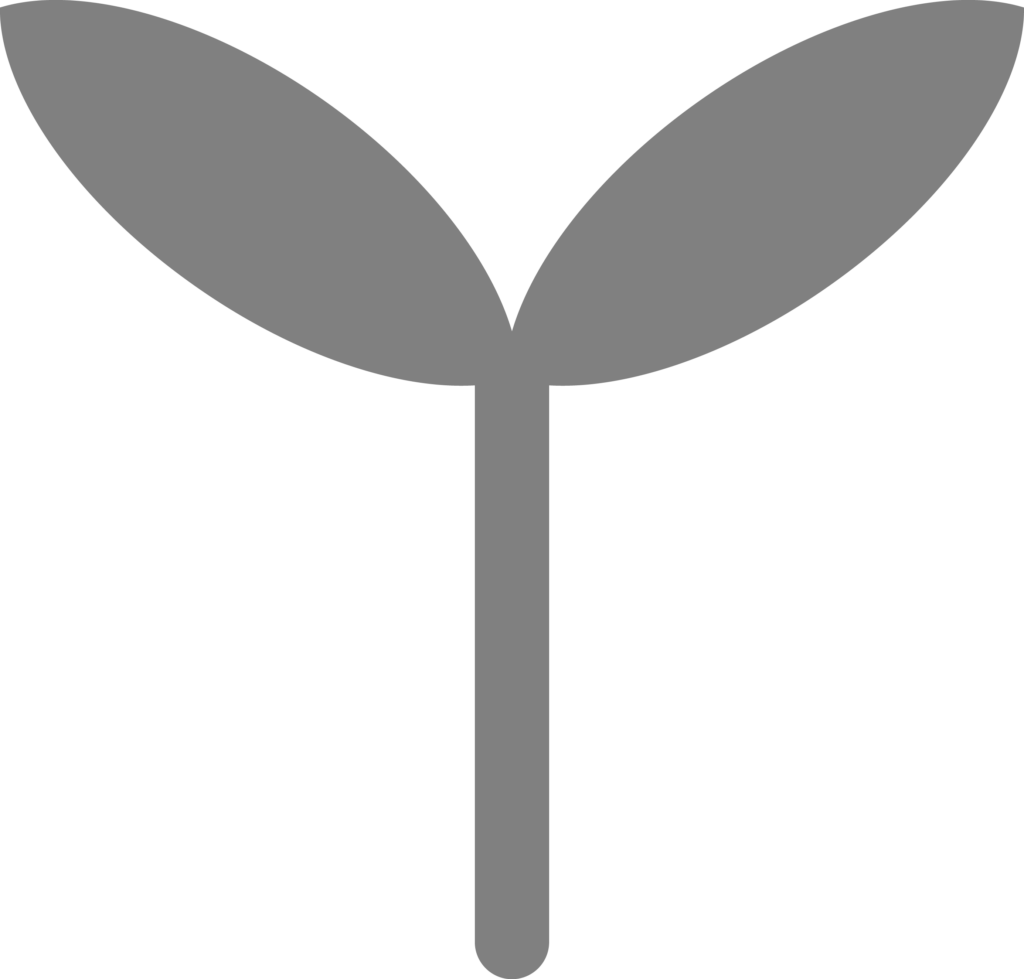
7月2日、担当である環境推進課の方からお話を伺いました。以下、聞き取った内容をまとめます。(許可を得て録音したデータを元に要約しています)
-
実験地の詳細とこれまでの除草について
-
琴弾クリーンセンター跡地内に2か所と旧養父市場浄化センター(養父市)にて1か所。これまで草刈りは人力で行っていた。人力が限界だったというわけではない。除草剤を使ったことはない。
ヤギを導入するにあたって、土壌汚染の検査は未実施。ふもとに集落があるため、水質検査は行っている。
-
実験の内容や方法について
-
元々設置されていた柵の内側で、ヤギを放し飼い。レンタル時に小屋と塩もセットで付いてきたため設置。
常駐の職員はおらず、3日前後毎に1回、水交換と確認のために訪問(連日行ったこともあれば、連休により5日近く行かなかったこともあったかもしれない)。課の人間3~4人くらいが交代で行っていた。
水は大きな容器に入れており、訪問時に水が無くなっていたことはなかった。容器は小屋の内側に置いたこともあれば、日向に置いたこともあった。
-
ヤギへの専門性について
-
飼育の際、ヤギに専門性のある人は関わっていなかった。レンタル時にレンタル業者から聞いた飼育方法を実践した。「基本的に世話はいらない」「水交換だけで良い」等の内容だった。業者のスタッフが状況の確認に来たことは無い。
-
亡くなったアンディについて
-
日差しのあたる所で亡くなっていた。発見時、遺体は綺麗だった。口から唾液のようなもの(血なのか嘔吐物なのかはわからない)が出ていたような気はする。職員が触って死亡を確認。痩せていたか等はわからない。暑い時期だった。
死因は調べておらず不明。遺体は手続きの上、保健所にて処分。亡くなる以前、体調が悪そうな様子はなかったと思う。死亡時に業者に連絡。来て調べるかと思ったが、業者は見に来なかった。写真を送ると、「外傷がないから原因がわからない。もともと調子が悪かったのか、レンタル中に悪くなったのかも判断できないから、養父市の方で処分してもらったら大丈夫」との返事だった。
-
施設の除草の必要性は?
-
施設管理上、除草はどこのセンター跡地も行っているもの。全体的に草が繁茂しているわけではないが、草刈りは必要。
一部地元の要望もあって公園化している。地元の方がメインで使われるため、一般に広く開放している状態ではない。門扉があり、普段は入れない。地元の協力を受けながら運営していた処理場なので、適正な管理をするように取り組んでいる。
-
今後、ヤギの草刈り事業は行うのか?
-
コストと手間のことを考えながら検討していく。今年はコスト面等から実施はしなかった。レンタル料とヤギを預かりに行ったりする手間がかかった。ヤギのレンタル業者に関しては、兵庫県にも値段が高ければあったかもしれないが、総合的に判断して決めた。
新聞では「期待外れ」という表現がされていたが、大失敗というほどのものではないと思っている。
日常的に人がおらず、ヤギ達の安全や健康のチェックが行き届いていなかったことが窺えます。水が空になっていたことはないそうですが、あくまで結果論であり、何かの拍子で無くなっていたかもしれません。
アンディが亡くなった際、死因を解明しなかったことも問題です。感染症や寄生虫、植物による中毒症、熱中症等、様々な要因が考えられ、リリちゃんが感染・発症する可能性も十分にあります。病理解剖を行い、リリちゃんに対しては獣医師による健康診断が行われるべきだったと思います。
レンタル業者の対応も不十分且つ不適切であったと考えます。
山々に囲まれた養父市は、ツキノワグマを始め、多様な野生動物たちが棲息しています。今回の現場は山の中。遺体が数日放置されている間に、動物たちが遺体を食べることも充分考えられます。これは、野生動物たちからすれば自然なことですが、彼らにとって不本意な誤解が生まれてしまうかもしれません。
生存に最低限必要な物だけ与えられて、知らない山の中に隔離され続けたヤギ達。とても胸が痛みます。
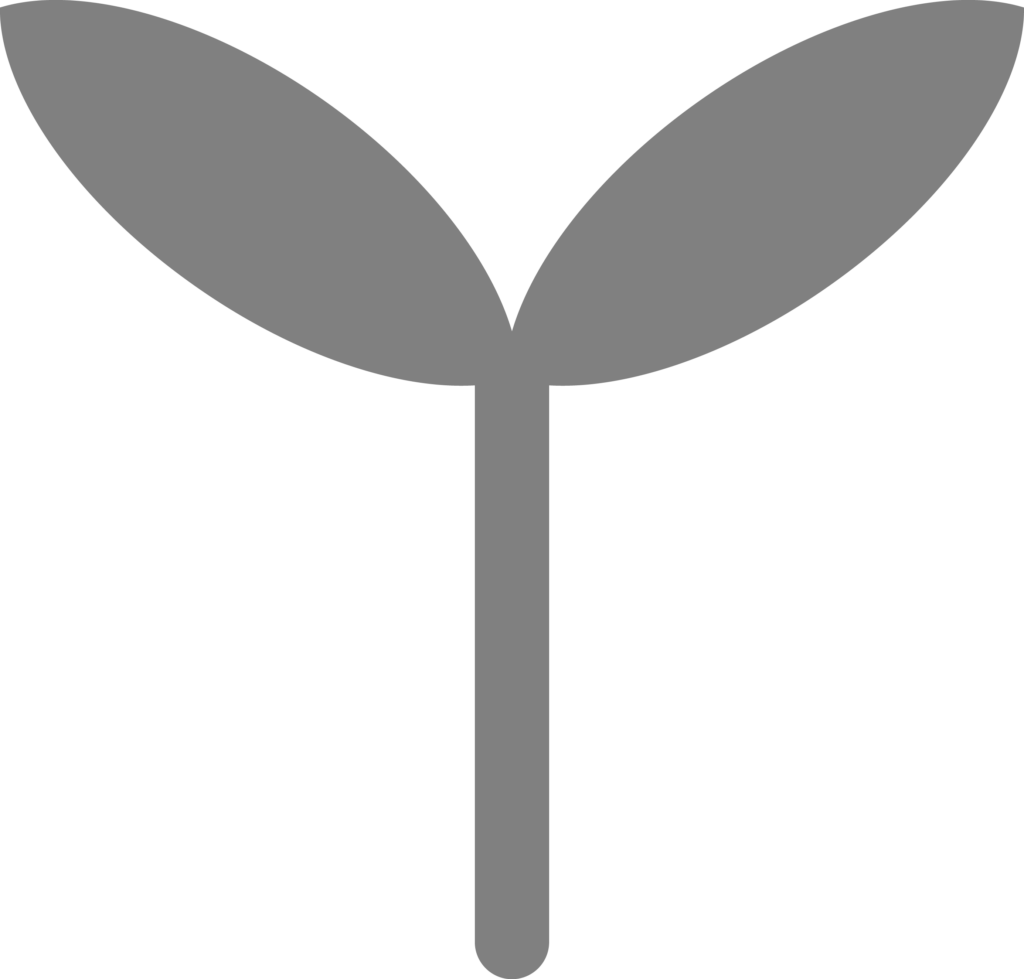
琴弾クリーンセンター跡地の場所を伺ったので、聞き取りの後に訪問しました。

実際の実験地点はゲートよりもっと奥のため、
ここからは見えません

日差しがとても強く、ムシムシとした真夏日でした。アンディが亡くなった時期は、どれほどの暑さだったのでしょうか...


曲がりくねった山道を登った場所にあり、
市街地がとても遠く下に見えます。
災害の際、ヤギ達を保護しに来ることは
出来るのでしょうか
後日、追加の調査等を重ねた上で、養父市長に向けて
"市の事業として動物を利用した除草を行わないでほしい"
"市内における動物利用事業の見直しを行ってほしい"
といった趣旨の要望と、その根拠を記載した要望書をお送りしました。
CO2削減は目指すべきですし、作業の負担が軽減されるのは望ましいことです。しかしながら、その役割をヤギ達が背負う謂れはありません。
どうか、動物たちへの配慮あるご回答をいただけることを願っています。
担当課の皆さま、この度はお時間をいただきありがとうございました。